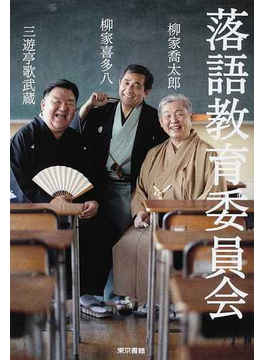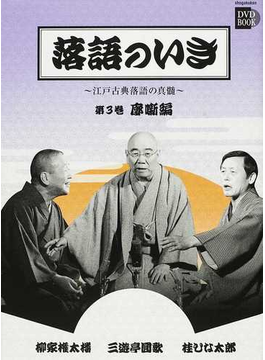
古今亭志ん吉「子ほめ」
続いて古今亭志ん吉さんも前座噺で、子ほめ。 おかげさまで最近よく聴かせていただいている、誰にでも安心してお勧めできる二ツ目さん。 この人はまったく一門以外の人。 先代圓歌の一門も数多いのになんで顔付けされているのかなと思っていたのだが、ヒザの橘之助師によると、笛吹きで参加しているのだそうだ。 なるほど、この芝居で交代出演の5人の二ツ目さんのうち、柳家花ごめ、春風亭一花のふたりは少なくとも笛吹きなのを知っている。 あとの三遊亭わん丈、三遊亭伊織(この人は一門)のふたりについても、調べたら笛吹きなんだそうだ。 今から噺家を目指す人は、笛を稽古するといいですよ。前座が明けた後仕事のない、「二ツ目地獄」に陥らなくて済むから。 春風亭一朝師なんて、笛で歌舞伎座に出てたのだ。 子ほめも、前座以外からもよく聴く噺だが、決して飽きることはない。 結構長い噺だから、マクラは短めになる。 今さらながらひとつ気づいたことがある。八っつぁんの「どうりでお顔の色が黒くなって」というセリフ、褒め言葉として使うパターンと、あとで持ち上げるためにいったん落とす前振りとして使うパターンがあるのだということ。 志ん吉さんのは、明確な褒め言葉としてである。三遊亭多歌介「浪曲社長」
圓歌師の弟弟子、三遊亭多歌介師は初めてだ。 圓歌師の漫談で、「バーコードに魔法の黒い粉を振り、ドライヤーを掛けようとしたところ計画停電になった」ネタに出てくる人。 寄席で見かけないのは仕事がないからではなく、全国を講演で飛び回っているためだそうで。昨年は(どういう基準だかわからないが)講演数日本一になったそうだ。 マクラの中で、「50歳だ」と語っていたが、1966年生まれだから52じゃないか。生年月日公開していながらサバを読む人は珍しい。 髪の毛が黒々としているのは魔法の粉のおかげなのか。 さすが講演が多いだけあり、手慣れていて楽しい漫談。 嘘つきだった師匠、三代目圓歌の思い出をいろいろ。さすがに、披露目の主人公である当代圓歌師のやるネタとカブるものはひとつもない。 ひとつ気になったのは、「よんだいめ圓歌襲名披露へようこそ」と語っていたこと。 え、「よだいめ」でしょ? しかし、この謎については、披露目の口上でわかることになる。 多歌介師、漫談だけで終わってもいい感じ。 だが、師匠から引き継いだ噺だと語り、浪曲社長へ。 私、オリジナルの浪曲社長、かろうじてTVで聴いて覚えているのである。その頃もう、中沢家は始めていたのだろうか? 「浪曲」のこともよくわからない子供であったが「姉がひとりにおととがひとり。弟ぼくより年が下」なんてフレーズ、耳に焼き付いている。 なんだか懐かしくなってしまいました。三遊亭歌武蔵「稲川」
歌武蔵師は、例によって「ただいまの協議について」から。 先に出た仙三郎社中の太神楽について、「最近の磁石の発達はすごいものです」。 ストレート松浦先生にこう言っているのも聴いた。 歌武蔵師は、「よだいめ圓歌襲名」と言っていた。 さてこのブログでも書いたのだが、私は「とにかく笑ってください。面白くなくても笑ってください」という噺家の挨拶が大嫌いだ。 これが遠因になったのだと思うのだが、演者3人討ち死にした神田連雀亭ワンコイン寄席も今年は経験した。 だが、同じテーマであっても、さすがに歌武蔵師は違う。 そもそも、所詮2,200円ぐらいでそんなすごい芸が聴けるわけもないこと、すでにおわかりでしょうと。演者だって、ウケないときに反省したりせず、客の悪口を楽屋で言いまくっているのです。 だから噺家に嫌がられたくなければ笑ったほうがいいんだと。 あの押し出し強い顔で言われると、笑う気になるではないか。 客はライトな落語ファンっぽいのだが、本当になにも知らないファンはむしろ少ないようで、歌武蔵が相撲上がりだと聴いてびっくりする人はいない。 おなじみ支度部屋外伝を振る。貴闘力(相撲協会、野球賭博で解雇)と同期と語っていたが、この人に対し1勝1敗だという対戦履歴はカット。 その代わり、焼肉屋として成功している元貴闘力の話が入る。最近メールが来て「天皇賞獲ったぞ」。お前、反省してないだろう。 そこから、笑えと言っておきながら人情噺である。夏場所初日なので、相撲ネタにしたようだ。 相撲人情噺の稲川。歌武蔵師が掛けるとは聞いていたが、聴いたのは初めて。 実にしみじみといい噺。落語に出てくる人情にもいろいろある。 披露目の席にも向いた演目。 こういういい人情噺を聴くと、先日人情噺をdisったデイリー新潮に一層の怒りが湧いてくる。 続きます。