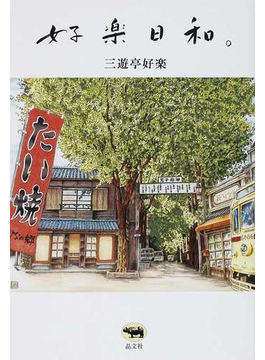
「令和最初の落語」は前座の西村さんだった。それがどうということはないけど、下手な人よりは西村さんでよかったなと思う。
ちなみに決して老けた外見ではないけど、もう45歳だそうな。
高齢前座というのは一般的に言ってダメな人が多いのだが、西村さんは例外のようだ。
さて、ここから三連続で、芸人出身噺家の出番。
他にも、笑点特大号でおなじみの春風亭昇也さんとか、私のイチオシ、笑福亭希光さんとか、芸人上がりは多い。
お目当てのひとり、三遊亭とむさん。元「末高斗夢」。この人は久々だ。
笑点特大号でもおなじみの真っ赤な着物で登場する。この着物、ちゃんとしたところで作ってもらったのに、羽織紐の位置がやたら高い。でもウケるので直さないのだと。
大阪で90歳の運転手が運転する恐怖個人タクシーの体験から。
ヨイショの達人、らっ好さんの紹介。あ、一昨年に国立の一門会で聴いた「よいしょ太郎」らしい。
私の好きならっ好さんがマクラに出てくるのも、嬉しいものだ。
ちなみに、もともと上手い人と思ってはいたらっ好さんのファンになったのは、亀戸に、とむさんの代演で出ていたときだった。
とむさん、らっ好さんを「弟弟子」と紹介。とむさんは好楽師の弟子で、らっ好さんは好太郎師の弟子なので正確には弟弟子ではないのだが、この一門においては、直弟子も孫弟子も、ほとんど区別されないようなのは前から感じている。
よいしょ太郎はとむさんにとって自信作なのだろう。
ストーリーは変わらないが、登場人物のやり取りがより洗練されていて、楽しいもの。
そして、妙に古典落語っぽいのである。
Facebookを駆使する現代の設定なのだが、やり取りの面白さがあくまでも軽く、エッセンスだけ抽出されている点が古典落語っぽいのだ。
といって、いにしえの芸協で掛けられていた新作落語のように「なんだ山田くん」というような、不自然なやりとりが入るわけではない。
三遊亭鳳月(ほうづき)さんは登場して、小痴楽兄さんの代演です。そんなに露骨にがっかりしないでくださいと。
物売りのマクラを非常に丁寧に。
代演で、まだ聴いたことのないこの人が出ると知り、事前に調べてから来た。
東京吉本所属の兄弟漫才コンビ「若月」の兄だったということだが、私はこのコンビのことをまったく知らない。
しかしWikipediaになぜか詳しく載っている。
とにかく、芸人上がりであることを知って聴くと、実に端正な古典落語なので、ギャップにいささか驚くではないか。
でも、きっと明確に目的意識をもって修業に励んでいるのだと思う。違うジャンルの経験は、落語の基礎を身に着けてから活かせばいいということだろう。
孝行糖も久々に聴く。
落語協会から三遊亭らん丈師。
先代圓楽の旧仇である円丈師の弟子たち、なぜかよく両国に顔付けされている。
議員だというような自己紹介はしない。
古典落語「宗論」に進む。意外と言っては失礼だが、なかなか楽しい。
その理由は簡単で、高座に終始冗談が漂っているからだ。こういう持ち味の人なのか。
実に軽い宗論。讃美歌もないし。
ギャグをやり過ぎず、控えめにする方法論のようである。疲れなくていい。
息子のほうは、長島さんみたいな横文字多用だが、その部分に対しては、親父が突っ込まないのもおかしい。
