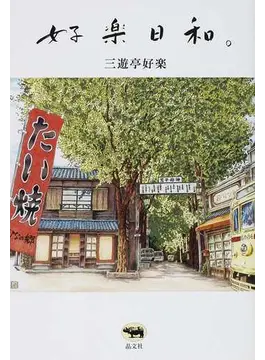今日はブックレビュー。
昨日もマンガレビューだったのだが、文句の吐き通し。
吐いてるほうも気分爽快というわけじゃない。口直しを。
今日取り上げるのは、最近ずいぶん頻繁に広告を張っている、好楽師の新刊です(2021年12月末発行)。
自分では買わず、図書館で借りてきました。ビンボー人なのでご容赦を。
お詫びと言ってはなんですが、精一杯宣伝に努めます。
好楽師の肉声がページから聴こえてくる、実にいい本である。
好楽師にインタビューし再構成した人は、実に手練れだ。間違いなく、書いた人も好楽師が大好きなのに違いない。
奥付に「編集協力」とある方の仕事だろうか。
好楽師の思い出は、さまざまな方面に溢れ、とめどなかったはず。その中身を芸人単位で再構成するのは大変だったろう。
軽快な語り口であっち行きこっち戻りする好楽師の姿まで目に浮かぶ。
ああ、オレも名前出なくていいからこんなゴーストライターの仕事したい。
ください。
私は好楽師匠の本業はもちろん大好きだし、笑点のポンコツ振りだって結構好きだ。
このふたつは恐ろしく対極にあるようで、実は隣り合わせ。
たびたび好楽師の魅力を書いているにもかかわらず、当ブログの記事の中ではアクセスも普通。孫弟子のけろよんさんの記事のほうがはるかに集客していて、ずっこけ気味。
世間の人は、好楽師につき、笑点のポンコツのままでいてくれるよう期待し過ぎてるのではなかろうか。
好楽師の落語に非常にいい味があることを知ると、自分の中の何かが傷つき、困るのかもしれない。
というか、笑点メンバーについてはみなヘタクソであって欲しいと切に願っている人も多そうであるが。
そんなおかしな期待は、短い人生におけるムダです。
好楽師が肉声を発しているこの本は、取り上げた芸人を客観的に眺めるスタイルではない。
すべて、好楽師の体験した、そして追憶という主観により書かれている。
好楽師が好きなら、そのフィルターのかかりようがたまらない本。芸人を語りつつ、自分語りも濃厚。
あの談志だって、いい人に見えてくる。正確には「談志は本当はいい人だった」というより、「私(好楽)は多面的な談志の、こんな側面も見てきたんだ」という語り口。
いっぽうで読み手の中には、好楽師の自分語りをスルーしてしまう人もいそう。つまりそういう、出しゃばらない肉声なのだ。
これもまた、師の大きな魅力のひとつ。業界における師のカリスマ性まで見えてくる。
好楽師は、二人の師匠である先代正蔵と先代圓楽の思い出をいつまでも大事にしている。
当たり前のことに思うが、そうでもない。二人から引き継いだ噺をいつまでもやっていければという主義であり、これはオリジナリティを持って唯一無二でありたい思想と得てして対立するのである。
オリジナリティを求めた人は、正蔵の記事に一瞬だけ出てくる小三治であり、歌丸である。
そういえば、ずっと同じ番組に出ていたのに、歌丸の思い出が本の中にほとんど出てこないのは不思議。小三治もそうだが、酒飲まない人とのエピソードは、先代志ん五ぐらいで非常に少ないみたい。
大酒飲みとの逸話は、柳朝、こん平、小圓遊と実に豊富な好楽師。
ともかく、最近の好楽師の高座が充実しているのは、オリジナリティの追求ではなく、先人から引き継いだ噺をちゃんとやっていこうしているからこそ。
そう改めて思った次第。
どのみちまったく同じコピーなんてあり得ないんだから。人のよさを通過させることにより、先人よりよくなることも当たり前にある。
二人の師匠と同じように、志ん朝と談志にも深い敬慕を寄せる。このあたりはマクラでもしばしば聴くところ。
いろいろな師匠によくしてもらった好楽師、常に落語界で全方位外交を繰り広げている。
上方や立川流ともツーカー。
志の輔、談春とは仲良しなのに、志らくは寄ってこないって一言だけ書いてある。
今、落語界のプロデューサーといったら休業中の当代円楽師なのだが、円楽プロデュースのかなりの部分は好楽師が助けている、そんな気がするな。
そんな、書いてないことまで読み取れる。談志の扱いをめぐって小朝師に頼りにされた話は実際に書いてあるが。
チラっと林家九蔵襲名断念事件についても触れられている。
まあ、あらかた世間に報道されたとおりではあるが、「九蔵は林家のものです」と言わざるを得なかった市馬会長が、後で好楽師に詫びを入れた話が面白い。
あの事件について好楽師は、世間の大部分が自分の味方であると認識しており、それも高座で聴いた。
寄席に「よび」で出ていた名もない芸人のことも豊富に書き記してある。
いわく、先代圓太郎、古今亭甚語楼、柳亭春楽。
甚語楼と春楽のエピソードは亀戸で聴いた。本には載っていない逸話もあったのは嬉しい。
とにかく、好楽師が好きな方、そして昔の噺家の好きな方はぜひご一読を。
そうでない方も、この本を通して好楽師の魅力に触れてください。
そんなに筆を割いているわけではない、亡くなったとみ子夫人の魅力にまで触れられる。