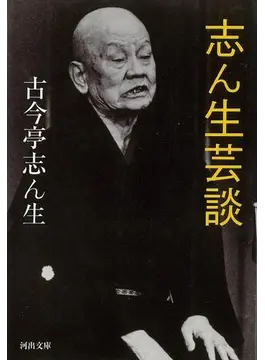NHKでやっていた「カラーで蘇る古今亭志ん生」を先ほど観ました。
没後50年。VIVANTに出てきたのもこれに関連しているみたい。
元の映像(「風呂敷」の高座)自体は、何度か観たことがある。なにせ、動いている志ん生というのは、ほぼこれしかないらしいのだ。
かれこれ20年ぐらいも前になるか、江戸東京博物館で落語展があって出向いた。その際も、オリジナルのモノクロ映像が繰り返し流れていた。
ちなみに、カップリングは圓生の「鼠穴」だった。
番組冒頭のトークは川口で収録したらしい。
知ってれば応募したのだが、9月1日この収録の裏、小平で東京落語会を聴いていたので当たっても参加しようがないけれど。
孫弟子の古今亭文菊師が司会である。あら、この人も六代目志ん生狙ってるのかしら。なんてね。
そして実孫の池波志乃と、人間国宝になったばかりの五街道雲助師。
緩いトークが面白い。実に噺家らしい。
志ん生宅の朝ごはんの話、インチキ将棋の話、志ん駒が磨き上げた床の話。
AIで蘇った志ん生の話を振られて、「えーあいもんだね」とつまらん洒落をかます雲助師。
文菊師が番組最中で語ったところによると、だいぶ長かったのを刈り込んだみたい。聴いた人は楽しかったろうね。
さて、久々に観た「風呂敷」で、改めていろいろなことを考えた。
- 個性が強いにもかかわらず、演者がまったく前面に出てこない
- 次のセリフをアドリブで作っている様子がよくわかる
- クスグリが伝わっていないとしても、全然気にしない
- 本編途中の脱線が、異様に長いが決してダレない
- 弟子・圓菊の使う所作が一瞬出ていた(町内のアニイ分が「俺に任せろ」)
ひと昔前は、マクラで噺家が自分の噺をしたりはしなかった。だから、高座の内容に、演者が登場してこないのはよくわかる。
とはいえこれはあくまでもスタイルの話。
志ん生の個性はあまりにも強烈で、スタイルを飛び出してきそうなのだが、高座の全体の印象としてはそうでもないのだ。
現代の落語はもちろんスタイルが違う。ただそのこととは別に、演者が噺の背景に隠れているのに耐えられなくなるところがある気がする。
なにも出たがりだからではなくて、噺を維持できなくなってつい語り手としてのツッコミを入れてしまいがちな気がするのだが。
志ん生になると、いつまでも隠れていることができるのである。
演者というものは噺のナレーターも時に務めるが、志ん生の場合、マクラからすべてがセリフで進んでいく。
一時期噺家しくじって講談やってた人にしては、講談の手法は皆無。
次のセリフを作りながら喋っている様子はよくわかる。
噺をセリフで覚えておかないから、こういうことができる。
これは現代の噺家も引き継いでいる人が多数いる。噺が予定調和にならなくていい。
志ん生といえばクスグリが名物。
マクラの小噺から炸裂している。
でも、クスグリをちゃんと伝えようとしていない。当時の客ですら、ヒアリングできない部分が多々あったと思うのだ。
伝わらなくても全然気にしていないし、伝えるのを目的にすらしない。当時の客は、雰囲気で大笑いしている。
お咲さん(名前は出ていないが便宜上)がアニイを伏し拝む。「お願いだよ」。
アニイが答える。「お願いだの手水鉢だのってなにを言ってやがんだ」。
意味がわからない。当時の客にもあまり伝わっていない。
その後、拝むしぐさを「はい(蠅)の親方みたいに」と表現するのはわかる。
<「帯がほどけてますよ」「どうもありがとう」これで一緒になったりするんですな>
これだけでなんで面白いのだろうか。
現代の噺家なら、伝わらないことがわかっているので前後を付け加えるだろう。その結果、何のために振られたのだかわからない、死んだ小噺ができ上がる。
「女三階に家なし」「貞女屏風にまみえず」「じかに冠をかぶらず」「おでんに靴を履かず」のことわざシリーズは、当時の客にもピンと来てないかもしれない。
それでも、「上げ潮のゴミ」「シャツの第3ボタン」あたりはその後も有名なクスグリとして存在を知られてるんだからすごい。
ゴミの了見も知らないでとアニイ。
お咲さんの場面も脱線だらけだが、アニイが家を出るまでもまた、長い。
アニイのかみさんはやたら強くて、いちいち言い返す。
このくだりも現代では聴いたことがない。噺が持たないのだろうから、カットしたほうが無難ではある。
でも、相談を受けてるアニイの家でも夫婦には揉め事(可愛いもんだが)があるというのは面白い。
志ん生はことさらに描写はしないが、このお咲さんはなかなか悪いね。
さらに前の時代はもっと露骨な描写があったみたいだが。
というわけで、実に刺激的で面白かった。
なお最後に断っておくが、別に現代の噺家はダメだなんて言う気はこれっぽっちもありませんので。
マネしてもどうにもならない部分は多々あるから、そこはスルーするしかないと思う。
見逃した方は再放送をお楽しみに。