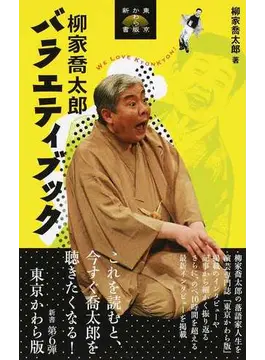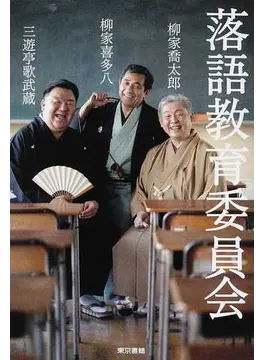先日久々に末広亭に行って、持ち時間の短さにより、変なところで切れてしまう落語を多数聴いてきた。
寄席、特に新宿がそういうところだというのはもとより理解している。
だが、そういう尺の高座が多数あり、その尺に合わせた落語が求められているにも関わらず、この業界、努力不足なのではないかという気がしてきた。
新宿が悪いのではなくて、尺に合わせた噺のできない噺家が悪い。
もっともっと、12分程度の噺を充実させていなければならないはず。新作でもいい。
特に寄席においては、他の演者とツかないように多種多様な噺が必要である。持ち時間が短く、演者が多ければ多いほど、噺が多数必要。
さらにいうなら、初席用にもっと短い噺だって用意しておいていい。小噺もいいけれど。
「噺を切ったらいけない」なんて言う気はまったくない。見事に編集されて尺に収まっていれば、文句など言わない。
「寄席なんてところは、つまらん噺家しか出ない」と書かれた書籍を続けて複数読んだ。寄席好きとしては歯がゆい限り。
ホール落語をメインに聴いている人が「待ってもいない人が出てくる寄席なんてつまらない」というなら仕方ない。だが、「生の落語なんてつまらない。家でCD聴いてたほうがいい」と言われたら、これはさみしいではないですか。
ひと昔前の噺家は、ウケる噺だけでなく、様々な噺を覚えておき、浅い出番深い出番、客の入りの程度、天気や主任の持ちネタ等あらゆる要素を考慮に入れて噺を選んだものだという。
現代の噺家にも、そうした努力が必要だろう。
さらに落語のネタ自体、まだまだ数多く必要だと思う。噺家も、落語会も増えたことだし。
新作落語自体は盛んだが、江戸・明治が舞台の、古典風新作落語ももっともっとあるといい。小佐田定雄氏の「幽霊の辻」なんて、私好きなんですが。
新作を作る以外でネタを増やす方法に、「滅びた噺の復刻」というものがある。
朝やっているNHKの「演芸図鑑」で掛けられるわずか9~12分ほどの落語、これもまた玉石混交ではあるが、しばしば玉のほうの掘り出し物があって当ブログでも結構紹介している。
本当によくできた短い噺なら「もっと長ければいいのに」とは思わないものだ。
前置きが長くなりました。
そんなことを考えているときに、演芸図鑑で柳家喬太郎師匠の「擬宝珠(ぎぼし)」が放映された。12分間の、至高の芸。喬太郎師の復刻による昔の噺である。
そういえば、もう15年くらい前だと思うが、初席の短い時間で喬太郎師の「寿司屋水滸伝」を聴かせてもらって衝撃を受けた覚えがある。さすが売れる人は、どんな環境でも、どんな持ち時間でもウケさせる。
売れっ子なのに、学校寄席にも行って「転失気」など掛けてくるそうである。しかも、前座のときに覚えそこなったので真打になってから覚えたそうで。これも、あらゆる環境に合わせた噺を掛けたいという努力の表れだと思う。
***
誰も掛けなくなった落語を、古い速記から掘り起こすのを得意にしている喬太郎師。しかも、揃いも揃って出来がいい。
誰も掛けなくなったその理由は、簡単にいえばつまらなかったからだ。
その、つまらない噺の、キラリ光る部分を見つけて膨らませ、独自のアレンジで甦らせる工夫、右に出る者がいない。
新作落語の第一人者だからこそできることなのかと思うが、しかし新作落語で売れている人だって、他にそんなことはしていない。
他にこんな仕事をしていたのは、上方落語を滅亡から救った桂米朝くらいだろう。だが、米朝は新作落語を多数作ったわけではない。「まめだ」と自作の「一文笛」は今でも人気の演目だけど。
そういえば、「やかんなめ」という噺も、もともと柳家小三治師がNHKの企画で甦らせたものらしい。これひとつだけ起こしただけでも立派な仕事に感じるが、複数掘り出している喬太郎師はさらにすごい。
古典と新作の二刀流、喬太郎師。実は噺の復刻を加えた三刀流なのである。極めてまれな才能だと思う。
喬太郎師は、常識人としての装いを効果的に使っている噺家さんだ。
尖った態度は決して見せない。見せてもギャグ。だが実際のところは、ディープな嗜好にまで理解が深く、感覚の冴えわたる人だと思う。
ウルトラマンなど、実際のところは極めてポピュラーな趣味のことではない。もっと異端の領域について。
だから、落語的常識の上にない円丈落語を自分のものとして消化できてしまうのである。円丈落語だけでなく、白鳥落語も、江戸川乱歩も小泉八雲もみんな消化してしまう。
噺の復刻が得意なのもうなずける。まさに落語の聖人。
喬太郎師は、「擬宝珠が舐めたい」若旦那の全体像を丸ごと理解できてしまう人なのだと思う。
ただ、ファンはここまでついていけないので、世間が理解できるような翻訳を加えてくれるのである。
***
「擬宝珠」は、元は初代三遊亭円遊の新作落語だそうだ。初代円遊は、「お初徳兵衛」を換骨奪胎して「船徳」を生み出した才人。
才人の噺を才人が甦らせるという、宮大工のような芸の伝承の世界、落語の世界もなかなかカッコいい。
「芸の伝承」とは、教わったとおりに噺を喋ることではない。そして、これは昔からそうだったということ。
「金物舐め」が趣味の若旦那の噺である。
橋の欄干など、今までも夜中にこっそり舐めていたが、浅草寺五重塔のてっぺんの擬宝珠が舐めたくなり、叶わぬ夢と寝込んでしまう。
昔の人は聴いてグロテスクに感じたかも。「金物舐め」などもちろん一般的な嗜好ではあり得ないが、現代人は変わった趣味嗜好であっても、「人それぞれ」だと、なんとなく受け入れてしまえるようである。
喬太郎師の復刻ではないが、やかんをなめて癪を治す「やかんなめ」も、現代に甦ったのは、同種の理由が背景にありそうだ。「やかんなめ」も、冷静に考えたら気持ち悪くなっても仕方ない噺だが、「いい噺」のフレーバーが加わっている。
噺の中にも「ライスカレーを箸で食べるという、金物の味が嫌いな人がいる。嫌な人がいるということは、あべこべに金物の味が好きな人もいる」という若旦那のセリフが出てくる。
箸でライスカレーを食べる人、というのは喬太郎師の弟弟子、喬志郎のことだそうだ。「落語こてんコテン」に書かれているエピソード。
なるほど、こういうところをヒントに、噺に肉付けをしていったのだ。だから「金物舐め」の嗜好にリアリティがある。
「擬宝珠」はマンガっぽい噺だから、真に迫ったリアリティまでは不要だろうが、客に噺を受け入れてもらうための最低限のリアリティは必要だ。
その結果、「若旦那、五重塔の擬宝珠が舐められてよかったね」、という感想を客が持てないと、聴いてあと味が悪くなる。
冒頭、重病の若旦那に、古くからの友達が真相を聞き出しにいくという、「崇徳院」の枠組みの借用もまた効果的である。
もとの「擬宝珠」では、なじみの幇間が若旦那に病状を訊きにいくことになっていたそうで、「崇徳院」を借りてきたのは喬太郎師だと思う。見事な本歌取り。
「千両みかん」にも通じる、安心して浸かれる落語の世界観があるからこそ、一見気味の悪い噺も楽しめるのである。