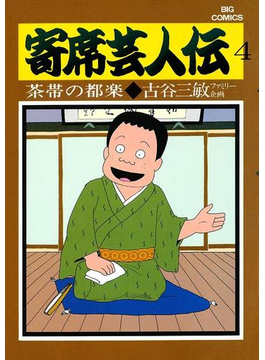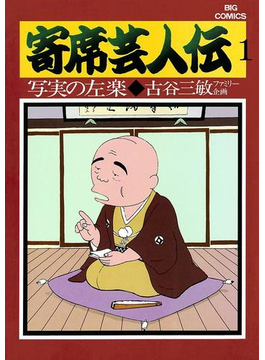久々に「寄席芸人伝」を取り上げる。
「寄席芸人伝」は、よくできた古典落語と同じように、登場人物が記号化されている。
まあ、マンガだから当たり前ともいえるけど。古谷三敏のシンプルな絵、それから同じ顔の人物が設定を変えて繰り返し登場する「スター・システム」が、記号化に貢献している点も見逃せない。
記号化の成功により、繰り返し読むと、各エピソードが読み手の頭の中にスッと格納されていく。
格納されたそれが、現実の事象に応じてときどき勝手に引っ張り出されてくるのだ。そういうときに、このブログで取り上げたくなる。
第四巻から、「第50話 横紙破りの橘丸」。
寄席の楽屋で、次の真打昇進予想をする噺家たち。
下馬評では「鶴助」。病気の師匠の世話を十年以上続けている噺家で、人柄がいいものの芸のほうは伸び悩んでいる。
対抗馬が「橘丸」。こちらは素行不良で、たびたび警察の厄介にもなっている男。楽屋でも、博打とヒロポン。
今日も出番を控えているのに、「急にタレがカきたくなって」いなくなってしまう。
やっと戻ってきた橘丸、使用直後のロセンを、前座にマンダラで拭けと命じる。
傍若無人で噺家仲間に評判悪い橘丸だが、師匠の善橘も、捨てがたい芸を持つ橘丸に小言も言いづらい。
またある日、具合の悪い師匠の世話のため、浅い出番にしてくれと頼む鶴助。
橘丸もまた浅い出番にしてくれというのだが、理由は吉原で馴染みに約束をしているため。とんでもねえと叱られ、やむなく高座に上がって適当に小噺を掛けるものの、実に器用な高座。
蓋を開けてみたら、真打昇進は橘丸のほうだった。
なんでだと、大看板「圓左」を追及する噺家たち。圓左は答える。「芸人の優劣を決めるのは腕だけだ」。
「腕の悪い医者にてめえの体まかせるか。ノコの使い方のわからねえ大工に普請頼むか」。ぐうの音も出ない噺家たち。
真打が決まり、高座でもって「あたしの実力からしたら当然ですが」と語る橘丸。楽屋連中、それを聴いてまたカーッとするが、圓左は袖から「小さくまとまった小利口な芸人が増える中、頼もしいぜおめえは」と独白。
「タレをカく」「ロセン」「マンダラ」の意味のわからない人は、ご自分で調べてください。
ピカレスクな主人公に、爽快感を覚えるのが今回のエピソードのテーマ。
だが、ここに取り上げたのはアンチテーゼとしてなのだ。ここから得られる爽快感、わかりやすいものだが、落語の世界でははなはだ危険である。
「無頼」の魅力が漂うエピソード「横紙破りの橘丸」。
師匠の世話をしている「鶴助」のほうのモデルは明らかで、これは古今亭圓菊である。
圓菊は、脳出血以来半身不随の師・志ん生の世話をしていた。足腰立たない志ん生をおぶって寄席に連れていっていたのだ。
ようやく真打になってからも、口さがない連中からは、「おぶい真打」と言われたそうである。師匠をおぶって、親孝行で真打になれたのだと。
それでもその後の圓菊は、一定の高い評価を維持し、古今亭の総帥として亡くなったからよかった。菊之丞はじめ、弟子も多い。
いっぽう、主人公「橘丸」のほうには、具体的にこの人がモデルというのがあるのかどうかわからない。まあ、昔はこんなエピソードを彷彿とさせる芸人が多かったのだろう。
落語を好きな人は、そういうものを解するはず。
だが、真の無頼は落語界には実のところ居場所がない。そのことも、落語を知るにつれわかってきた。
談志は破滅型芸人が好きだったらしいが、結局のところ、破滅してしまうから破滅型なんである。破滅型芸人になっていいことはない。
二代目春風亭梅橋や、瀧川鯉昇師の最初の師匠である八代目春風亭小柳枝などが破滅型の芸人として知られている。
前者は、吉川潮「落語の国芸人帖」に、後者は瀧川鯉昇「鯉のぼりの御利益」に詳しく書かれている。
落語そのものはあまり知られていない。破滅型芸人は、こういう「エピソードがあった」ということでしか落語史に残らない。
現代、真に無頼な芸人は少ない。橘家文蔵師だって違う。
橘丸のような人が、その後どうなるか。マンガだからストーリーは真打昇進が決まっておしまいだが、この後間違いなく、仲間もなく高座もなく淋しく死んでいくのである。
落語はひとりでやるもの。だが落語界とは、一般的なイメージよりもはるかに「和」を重んじるところだ。
それどころか、もともとチームプレイに向いた人が入ってくる業界なのだと、三遊亭萬橘師は言う。
寄席に通い見事な芸を楽しむうちに、チームプレイのこの重要性が私にも沁みついてきたのである。
最近続きもので、「立川流」について、自分たちだけが一流だと思っているその傲慢さを取り上げたところである。
そこで、「寄席芸人伝」のこのエピソードを思い出したのだ。
落語界の無頼・はぐれ者に対し、ファンが魅力を感じるのも、噺家志願者があこがれるのも、感覚として非常によく理解できる。
だが、そんな師匠にはつかないほうがいい。
寄席に出られない、出ようとしない立川流においては、「チームプレイ」の重要性が沁みついていくこともないのだ。いきおい「一匹狼の集団」化していく。
「一匹狼の集団の分裂」が今起こり掛けていて、いやはや。
落語界全体に対して喧嘩を売り続ければ、同じ立川流の噺家にも喧嘩を売っていることに、やがてなる。談志没後の分裂は不可避。
大事なことだが、立川流と違って円楽党は、けっして自分の巣にこもってはいない。
「和が大事」だなどと改めて主張するのは面はゆいところがある。私生活においては、私はまったく他人との調和を重んじる人間ではない。むしろ立川流にシンパシーを感じても不思議のないはぐれ者である。
だが、それでも私は落語が好きで、寄席が好きなのである。であれば、好きな世界を維持してもらうため、噺家さんたちに調和を期待しても当然だろう。
自分の性格に似た芸人に期待しても、見返りなどなにもない。
東京に比べると、上方落語界は、協会が一本化されているわりにまとまりが悪いように映る。
所属事務所が強いからというのもあるだろうけど、私は寄席の歴史が途絶えていたのが主たる理由だと思う。
でも、繁昌亭に加えて神戸にも「喜楽館」ができる。20年も経てば東京のようになっているに違いない。
それこそ落語の本質ではないかと思うのだ。