前回珍しく、「寄席芸人伝」のエピソードを、共感する対象としてではなく使ってみた。
だがもともと、「寄席芸人伝」の世界自体、非常に緩い。
「厳しい修業に耐えて開花する噺家」というテーマが根底に流れているようでいて、平気でそれを裏切るエピソードが入っている。
だからこそ、押しつけがましくなく楽しいのである。
人に特定の思想を押し付けてくるうっとうしいマンガもある中で、そういう緩さがたまらない。落語にも通じる緩さである。
「横紙破りの橘丸」で取り上げられていたのは無頼な噺家の「憎まれっ子世に憚る」という活躍である。
だが、同じ「寄席芸人伝」の四巻に、いきなり真逆のテーマが入っている。
今度は無頼から足を洗うエピソードなのである。続けてそれを。
「第55話 小博奕三好」。三好は、もちろん「さんこう」と読む。
バクチに余念のない噺家三好が高座で「狸賽」を掛けている。
バクチの噺は、壺を振る仕草を含めてやたら上手いという、楽屋雀の評判。
前座が泣いているのでワケを訊くと、三好に、「看板のピン」そのままの手口で引っ掛けられて、小遣いを巻き上げたと。三好、ひでえじゃねえかと仲間に言われると、「世の中の厳しさを教えてやったのさ」。
またある日、噺家の通夜の席で「パーッと楽しくやりましょう」とバクチ場にしてしまう。
警察が踏み込んできて、通夜はめちゃくちゃ。当人はとっとと逃げてしまう。
翌日平然と高座で「へっつい幽霊」を掛ける三好。
噺家たちは師匠のしん好に、なんとかしてやってくれと言うのだが、「芸は荒れてないようだから」と腰の引けた師匠。
しかし大真打「橘家圓蔵」が見かねて、「どこを見ていなさんだ。大荒れじゃねえか」。
圓蔵いわく、「奴の目がいけねえ。噺家の目じゃねえ、バクチ打ちの目だ」。それが客に伝わって、ウケなくなっている。
圓蔵が三好に、「小博奕をやめて、落語で大博奕をしてみねえか。おめえさんなら天下が取れる」。
それを機に、バクチを止め落語に専念する三好。ある日の「狸賽」では、すっかり壺を振る仕草が下手になってしまった。
だが、圓蔵は、「これでいい」。大らかないい味が出てきたと評する。
「小博奕三好」のモデルは、三代目桂三木助だろう。この人は、「隼の七」と二つ名のついた、本物のバクチ打ちだったという。
三木助と盃を交わし、義兄弟の契りを結んでいた先代小さんにも、小きん時代に「壺の振り方ばっかり上手い」と客に陰口を叩かれたというエピソードがある。当時の壺の振り方は、三木助に教わったリアルなものだったらしい。
小さんはその後、「壺の振り方なんか適当でいいんだ」と言うようになったとか。
落語のリアリティが現実のそれと違うことを物語るこのエピソードは、「寄席芸人伝」にも盛り込まれている。
通夜の場でバクチに興じている噺家の姿は、先日亡くなった三遊亭圓歌の漫談「昔の芸人」などでよく聴いた。坊さんまでバクチに巻き込んでいるのも同じ。
バクチ場になるのがいいことかどうかは別にして、噺家さんの葬儀はパーッとやるのは今でもそうらしい。
さて、男の三道楽は「飲む打つ買う」である。実際、噺家もまた、三道楽に手を出すものだとされている。「モートル」なんて隠語もあるし。
だが、落語においてこの三道楽の扱いは、実のところ相当に違うものである。
酒の噺は、「試し酒」「禁酒番屋」「親子酒」など、聴いてて飲みたくなるものが多い。「棒鱈」みたいな酒でしくじる噺もあるけど、酒はだいたい肯定されている。
いっぽう廓噺になると、失敗譚が多いようには思うが、それでも「明烏」「幾代餅」「錦の袈裟」「木乃伊取り」「二階ぞめき」など、廓を夢のテーマパークとして描いた噺もかなりある。
それらに比べると、バクチは扱いが相当に違う。
「看板のピン」とか「狸の賽」など楽しいバクチの噺を聴いても、そこに参加したいとは思わない。欲にくらんで失敗する噺ばかりであるし。
「バクチの魅力」そのものを描いた噺など、聴いたことがない。
バクチの魅力を描いた作品自体、落語の外に目を向けても非常に少ないのだが、それでも阿佐田哲也の「麻雀放浪記」をはじめとするギャンブル小説、福本伸行の「カイジ」をはじめとするギャンブルマンガなど、一応存在している。だが落語にはない。
昭和の名人三遊亭圓生(六代目)も、「バクチはいけませんよ」と言っていたらしい。理由は、寄席芸人伝のエピソードのままだろう。
女好きとしても知られた圓生、いっぽうで噺家が女に手を出すのは大賛成だったそうである。こちらもちゃんと理由があって、噺に色気が出るからいいのだと。
ちなみに、作品中に大真打「橘家圓蔵」の名前が出てくる。この名前は圓生も名乗っていた。かつては、橘家は三遊亭のセカンドブランドだったのだ。
本質的に落語には、バクチと相容れないなにかがあるようだ。
先に挙げた、バクチの魅力を描いた作品を読んでも、落語らしさと共通する場面はない。ふわふわした落語の世界と異なり、とにかく息が抜けないのである。阿佐田哲也(色川武大)など、演芸に造詣が深かったにもかかわらず。
バクチは、人生における生来の喜びではないんでしょうね。
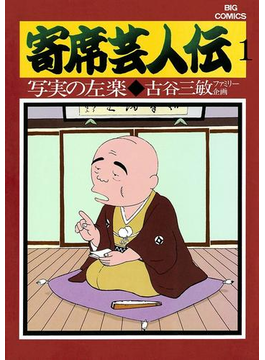 電子書籍全11巻セット
電子書籍全11巻セット