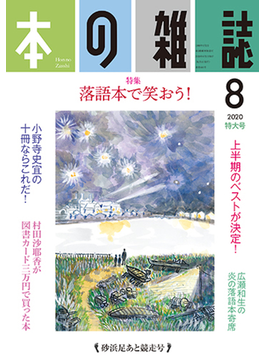さて古典落語においては、女性語は必要ではない。
長屋のおかみさんの使う言葉は、亭主とほとんど変わらない。
ただ、「あーら」「おまえさん」「いやだよ」などのセリフを最低限の分量発せば、女が喋っていることが自然とわかるようになっている。さすがは伝統芸能。
識別がつくなら、どんなに口の悪いかみさんでも落語として成立する。
三遊亭遊雀師なんて、亭主より低い声を出すおかみさんだ。こんな荒業すら成り立つ。
落語の場合、声の高さで性別を描き分けない(声色を使わない)ので、男女の言葉を描き分ける際に、最低限のヒントは必要。
だが、現代の言葉で書いた新作落語の台本において、やや問題がある。
実際の高座で語る場合なら、新作でも女性語は使わなくていい。古典と同様、ちょっとしたしぐさや、一人称、三人称等のヒントで、女であることをわからせれば済む。
だが、台本は問題。
私も自作の落語を書いた際、女性が出てくるシーンでちょっと悩んでしまった。
脚本みたいに、セリフの前に「女1」と発話者を書いておくスタイルなら、気にすることもないのかもしれない。
三遊亭円丈師の台本もこうなっているが、そのスタイルにはしたくなかった。
講談社から出ているロングセラー「古典落語」(興津要・編)を、かつて星新一がエッセイで読みやすいと分析していて、これが記憶に残っていたのが遠因にある。この落語集には、発話者が書かれておらず、セリフだけなのだ。
セリフしかないとなると、女性であることをわかりやすくする必要がある。
そのため、「てよだわ言葉」を多少入れた。こんな言葉使い、現実には誰もしていないことは認識しつつ。
ところが面白いことに、敬語を使うシーンだと、最初から気にならない。
敬語の場合は最初から性差が少ない。はじめから、語尾で書き分けようなんて意識自体がなくなる。
小説にも同じ問題がある。
名前を出した星新一のショートショートも、女性語が、現実と違う使われ方をしていたなと思い出す。
男がずっと敬語を使い、女が最初から蓮っ葉な言葉遣いという不自然なパターンが非常に多かった。あちら立てればこちら立たず。
ただ、この不自然さに対する批判は読んだことがない。仕方ないことなのだろう。
現実に近いリアリティは失われるが、小説のデキについての傷にはならなかった。
英語落語のときはどうなるのだろう。三遊亭竜楽、桂小春團治、桂かい枝、桂三輝(カナダ人)といった人たちが、英語その他で落語をやっている。
英語落語を聴く習慣がないからよく知らないのだが、特にさしたる方法論などないのでは。
最初から性差の少ない言語の場合、真剣に考えるほどのことでもないはず。
竜楽師からはよく、マクラで外国語落語についてネタを聴くが、性差については聴いたことがない。あまり意識はしていないものと思われる。
恐らく因果関係が逆なのだろう。
最初から性差が存在する言葉だからこそ、日本人は女性語をつい使ってしまうのだろう。
そう考えたほうが、TVバラエティの翻訳問題は理解がしやすい。
言葉に内在する貴重な性差を、演出上活用しない手はないと考えたくなるのだ。
性差を強調する演出については、批判は多いし、私もまたそう思う。だが、積極的な意味が見出せるからこそなくならないのだ。
まあ、フェミニストからは一切顧みられなかろうが。
最近、私は上方落語づいている。急に聴き始めたわけではないけども。
その、上方落語の手法でちょっと気になる部分がある。
新作落語で顕著な手法。女性の登場人物に東京弁を喋らせることがあるのだ。別に東京出身だという断りもないまま。
超ベテランの桂文珍師がこの手法を使う。若手でも、影響されてか使う人がいる。
これ、感覚的にはわかるのだ。いわゆる標準語というものは、関西人からはとてもフェミニンに聞こえるので、東京弁を喋らせると自然に女っぽくなるのだ。
文珍師は、この方法がむしろ自然だと考えているのだろう。ある種の画期的な発明ではある。
でも、本当に必要性があるのかね。
現代の関西が舞台なら、本来、言葉の性差はとても小さいはずなのだ。
性差のない言葉を喋らせればおいてはダメなのか? 描き分けのためにこうしているのなら、やはり不自然な感が否めない。
こういう手法が大嫌いということではないのだが、考え出すと止まらなくなる。