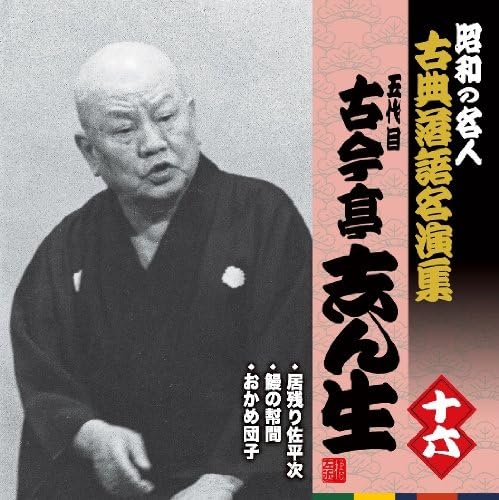どう着地しようか考えつつ進めてきたのだが、とくにひねりもなく、今日も古典落語の騙しの構造を観察して締めるとします。
一昨日に「騙し」の落語についてなにがあるかまずまとめたが、その後もさらに追加修正している。後で次々と思い出すものだ。
その中で、最後に付け加えた「禁酒番屋」が、「騙し」の落語の代表として、なかなかいいダシが出ている気がする。
最終日はここからスタートしてみよう。
落語において、「騙し」というものは価値観逆転の要素として現れる。当初は仮説だったのだが、おおむね間違いない気がしてきた。
価値観の逆転として、禁酒番屋は最適の例ではないか。
禁酒番屋における「騙し」は、酒屋の若い衆の復讐のために登場する。復讐といっても、ごくごく軽い。
この噺の構造から確認する。
- さる藩で「禁酒番屋」の登場
- 酒屋にお得意の藩士が来て、酒の注文をしていく
- 菓子屋に化けて酒を持ち込む(騙し)⇒発覚・没収
- 油屋に化けて酒を持ち込む(騙し)⇒発覚・没収
- しょんべん屋としてしょんべんを持ち込む(騙しを利用した騙し)⇒復讐成功
刃傷沙汰があったので、酒を一切飲まないことにする藩中。この価値観は、決して間違ったものとはいえない。
劇中でも、お得意先を失う酒屋の嘆きはあっても、禁酒令は別に非難の対象ではない。
噺家もだいたい地のセリフでもって、「お殿さま、自分も飲まないと言ったのは偉い」と褒めている。
最初の騙しの実行は、「酒ちょっと飲むぐらい、いいじゃないか」という価値観に基づく。
それにしても、こっそり持ち込んだらいいだろうという程度であり、武士に本気で逆らおうという反骨精神に基づくわけではない。だいたい、禁を最初に破ったのは酒屋でなく、酒屋にやってきてこっそり飲んでいる近藤さまのほうなのだし。
だから酒屋の若い衆も、詰めが甘いのだ。どっこいしょ。水カステラと言いつくろってももちろん番屋は見逃さない。
そして油屋もしくじり、計2升の酒を、「お役目」と称して飲まれてしまう。
番屋のさむらいの中にも、本音と建前という価値観の対立があるのだ。その点がこの噺はよくできている。
そして酒屋の若い衆が憤るその対象は、「禁酒番屋」の制度そのものではなくなっている。あくまでも、2升の酒を飲んださむらいが復讐相手になるのである。
最後の騙しはなかなか高度。騙しそこなった過去2件を伏線にした、新たな騙しだ。
しょんべん屋が申告通りしょんべんを持っていくのだから、なにも問題はない。
「正直者め!」というサゲは、実に効果的。
最後の騙しも、よく見ていけばそこにまさに価値観の逆転が見られる。
もういい、酒を持ち込むのはあきらめたというところから、真の騙しが始まるのだ。
普段はヘイコラする相手であるお武家をやりこめるというのも、またひとつの価値観逆転だ。
3日間の最後にもうひとつ。廓噺から選びたい。
廓噺で「騙し」というとおおむね男女の仲についてなのだが、ちょっと捻って「居残り佐平次」。
居残り佐平次が騙す相手は、女ではない。宿屋全体を騙してみせるのだ。
「居残り」という言葉はもともと存在する。カネがなくて勘定が済ませられない男が、人質として閉じ込められる。とても不名誉である。
佐平次が挑むのは、この確立された価値観である。「もしも明るい居残りがあったら」というのが、たぶんテーマ。
明るい居残りだけあり、佐平次からするとすべては予定の行動。散々楽しく飲み食いして、女とも寝て。
しかしそこからがむしろ真骨頂。
勝手に若い衆として働き、客に気に入られる太鼓持ちのようなプロ居残り。本物の若い衆としては気に入らないことこの上ない。
さすが佐平次、お店を騙しているのに、祝儀の減った若い衆以外は腹を立てていない。佐平次目当ての客までいて宿は盛況、主人もそれほど不服はない。
喬太郎師なんて、主人に「私はあなたにいてもらいたい」なんて言わせていた。佐平次のおかげで売上が大きく向上したのだ。新しい結城を取られたところでいかほどのものか。
無給でお店を盛り上げてくれる、こんな助かる居残りはいない。
だが、最後の最後は佐平次、見事に詐欺を働いて去っていく。自分は凶状持ちだから身を隠さないとならないのだと、さらに巻き上げる。
一見極悪人のようだが、やっぱりそうでもない。
既存の価値観に逆らい、二度トランスフォームするのが居残りの真骨頂である。