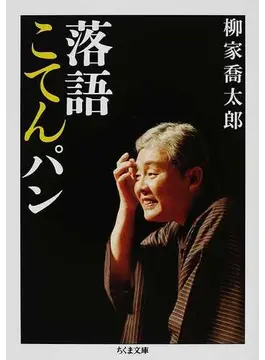若手も紙入れを競ってやりたがるが、私にはまったくピンと来ない。
彼らがこの噺のどこに魅力を感じているのかが、見えてこないのだ。
ノンフィクションを、状況設定を変えて語る設定に惹かれているのだろうことは理解しているけど。
設定が似ている「風呂敷」の場合、ウソ話は男を救い出すための方便である。だから自然。
それにくらべて紙入れのほうは、間男の新吉が、自分を追い込んでしまうのである。不自然極まりない。
このあたりが、私にスッと入ってこないようだ。
噺の枠組み自体に疑問を持っていたのだ。
喬太郎師、同じことを考えたかどうかまではわからない。ただ、若手とはまったく違う部分に焦点を当てて作り直す。
喬太郎師の紙入れの構成を丁寧に見ていくと、別の要素が見えてくる。
全体を、笑わせる場所と、しっかり古典落語の助走に使う部分とに、明確に分けているのだ。
だが不思議である。後者は本来、半ば義務的に振られるはず。
なのにみんな知ってる豆腐屋小噺が、やたらと面白く響くではないか。
与太郎に工夫を凝らしたり、間男話を広める男が「発表します」「解散」などとやっていたりするおかげではある。
固い部分を柔らかく語り、柔らかい部分は芝居仕立てで、微妙に固く見せる。すばらしいバランス感覚のたまもの。
客はもちろん、漫談でなく落語が聴きたい。漫談部分と落語の比率が絶妙なのだ。
古典落語の助走をしっかりやることの副作用が若干ある。
「町内」をちょうねえと発声し、「大好き」をでえすきと発声する。
師匠・さん喬にも指摘されていたと思うが、若干、誇張し過ぎの江戸ことば。
新作落語と同様、「ちょうない」「だいすき」でいいような気もする。
ただ、視点をもう一段外にずらしてみる。みんなで「江戸の町人ごっこ」をしているシーンだと考えると、決して悪くない。
喬太郎師は、古典と新作と、アプローチにおいてはスパッと切り分ける人だという認識でいる。
だが意外と、師においてはさほど違いがないのかもしれない、そんな気もする。
古典落語へのアプローチはさまざまだが、喬太郎師は噺を破壊するような改変はあまりしない。先人の功績を忠実に引き継ぎ、キョンキョンらしさは細かい部分に見え隠れすることが多い。
だが紙入れに関しては、噺の破壊こそしないが、音階自体を替えてアタックすることにしたらしい。
幸い、師には演劇の手法がある。
落語のリアルに迫らず、芝居のリアルを使って乗り切ることもできる。
3人の登場人物のうち、主人公の間男新吉と、おかみさんをコメディ芝居の手法で極めてユニークに描く。
おかみさんのポエムなセリフはたまらない。羽織の紐をぶんぶん回す所作は大爆笑。
以前聴いた紙入れと比較しても、相当に進化している。
しかし進化するにつれ、おかみさんはリアルな人間としての中身を喪っていっている。確信的にそうしているのだろう。
古典落語なんだから、喬太郎師の「紙入れ」を聴いて女の怖さをリアルに思い知るのもいい。だが、現在の喬太郎師の攻める部分、ちょっと違う。
やはり、コメディ・軽演劇要素のほうが強い。
女の怖さは、リアルには来ない。笑った後で密かにやってくる。
ただ、おかみさんが記号化すればするほど、リアルな人物である、ポエムなカミーレ夫人のことを連想してしまったりなんかして。
これをヒントにしていたならそれはそれで面白いけど、喬太郎師の確立のほうが時系列的に先ではあるだろう。でも、2021年にこの芸を披露することに、聴き手が勝手な意味を見出したりする。
いっぽうで新吉も、生身の人間からどんどん、コメディの一部に進化している。
歯を食いしばって喋る新吉。腹話術からヒントを得たのかしら。
落語には存在しないワザ。これに匹敵するのは、春風亭一之輔師の「口元を緩めてはきはき喋る与太郎」ぐらいのもんだ。
(紙入れが)「見つかりましたか」という、若手が最大のポイントに置く部分が、まったくウケてないのでびっくり。
全編爆笑、愉快な紙入れの、最もウケてない部分がここ。
いかに、一般的な古典落語とモードが違うかということ。
喬太郎師もここがウケないのを先刻自覚していて、旦那の返しは極めて速い。
客のほうも、若手からは決して得られない楽しさがすぐやってくるから、不満に思ったりはしない。
楽しいコメディの舞台を観た感覚。落語を感じないなんてことではない。
師の期待どおり、コロナ禍を生き抜く我々を勇気づけてくれる、見事な一席でありました。