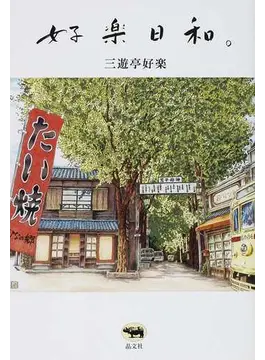昨日、「笑点メンバーはなぜ売れるか」という見出しを出したが、問題提起だけで結論が出ていなかった。
最終回、今日の記事で解き明かします。
ちょっと脱線するが、水曜日のラジオビバリー昼ズを金曜にようやく聴いた。
昇太師の番組である。そしてゲストが小遊三師。
浅草の「にゅうおいらんず」について。小遊三師はトランペット、昇太師はトロンボーン。
今度にゅうおいらんずはレコード(CDでなく)が出たのだ。
小遊三師は力が抜けていて本当に面白い。
一時期、小遊三師は昇太師の真打昇進時に配った扇子で高座に上がっていたのだという。ちょっと昇太師の熱さを見習おうと思ってとのこと。
それだけ、日ごろから緩い人なわけである。
笑点こそ落語(チームプレイについて)
落語というもの、寄席というものは、チームプレイ。
通っている人にとっては、常識中のジョーシキ。
もっともただの理念だろうと思っているファンも中にはいるはずだが、いったん「そういうものだ」と思ってください。
トリの師匠のために、他の噺家が盛り上げるための噺をし、そして色物さんが疲れた客の頭をほぐす。それが寄席。
全体としての素晴らしいデキを作り上げることが、顔付けされた全員の目的。
一人だけ突出して、ウケを根こそぎ拾ってやろうなんて芸人はいない。いてもしくじる。
寄席は、最初から「調和」を全面に置いて、期待される仕事をやり切る、そういう場所。
上方落語家ですら必ずしも理解しているといえないような文化であり、大変なものである。
さてチームプレイであり、一人も突出しないのは笑点もまったく一緒である。笑点大喜利は、まさに寄席の文化から生まれているのだ。
ひとりひとりにキャラが付いているのもうなずける。キャラが付くことで、「番組に求められる役割」が明確になるわけだ。
寄席でもこれはまったく一緒。寄席に呼ばれる目的はだんだん明確になってくる。
目的に抗うような行動をしていると、やがて干されてしまう。
寄席で期待される目的よりも、笑点のそれは深く、濃い。
三遊亭小遊三師は、笑点では泥棒であり、フランスかぶれであり、男前であり好色(多いな)だが、寄席では本格派でキレのいい滑稽噺を求められている。
三遊亭好楽師は、笑点では仕事がない男であり、ケチの競馬狂いであるが、寄席では二人の師匠から引き継いだ、豊富なバラエティを持った演目の演じ手である。
春風亭昇太師は、笑点では、「還暦なのに上ずった躁病のおじさん」だが、寄席では「会長なのに上ずった躁病のおじさん」である。
「噺家に上手いも下手もなかりけり 行く先々の水に合わねば」なんてことを言うのだが、笑点メンバーはどんな水にも合わせられる人たちなのであった。
この点、若手大喜利を視ていると、キャラが定まっていないことに気づく。
一番定まっているのが昔昔亭喜太郎さんなのだが、確実に出るメンバーでもないのは残念。
一昨日も書いたのだが、最近女流大喜利のほうが面白くなってきている。これは、女流のほうがチームワークが高く、おのおのの役割を忠実にこなそうとしているからだと思う。
笑点も落語も「お約束」
談志が作った笑点は、ブラックユーモアの番組だった。知らないけどさ。
笑点が現在のようなぬるい番組になっていったのは、ここまで筆を進めてきた結果、実によくわかるようになった。
噺家がやっている以上、なるべくしてこうなったのである。
そして、笑点の笑いなんて、そんなにすごいものである必要はない。
笑点は、お約束の世界。円楽師がいつもの腹黒キャラをぶつけて、いつものように客がウケる、そんなもの。
全力で笑点の偉大さを書き進めている私だって、子供の頃毎週視ていたその番組のぬるさにやがて飽き、離れていった。
寄席に通うようになってからも、別段笑点のことなんて強く気にしたことはなかった。
しかし最近とみに思うようになった。「なぜ寄席に通うか」という疑問は、自分に常に問いかけている。
「古典落語の繰り返しがもたらすある種の美学に惹かれているから」というのは答えのひとつ。これをマンネリズムという。
それはそうと、笑点といったいなにが違っているのか?
まだまだ続けられるが、あとは同じ話の繰り返しになりそうだ。
落語ファン、もっと笑点に目を向けて欲しいとは、それほど思わない。
ただ、落語を語るときにアンチテーゼとしての笑点を持ち出すのは、冷静に考えてとても恥ずかしいので、やめたほうがいいと思うわけです。
そして、笑点の「ぬるさ」「チームプレイ」に惹かれている人は、きっと落語が楽しめるだろう。