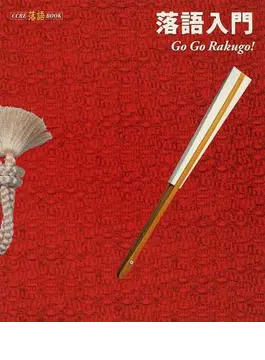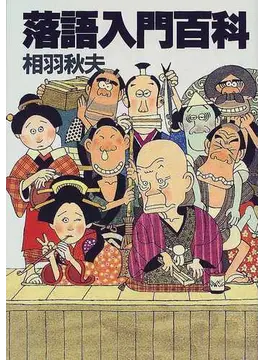「お後がよろしいようで」=「オチがついた」は誤解です 落語芸術協会に「正しい使いどころ」を聞いてみた
というコラム記事が出ていた。
さまざまなポータルに転載されているので、そちらでご覧になったかもしれません。
ン?と思った。正しい意味「あとの師匠の準備ができた」についてはいいのだ。
「筆者はこのフレーズを『収まりよくオチがつきました』という意味の決まり文句だと思っていた」とある。
そんな思い込み、私はしたことないな。そもそも、世間は明確にこの意味で使っているでしょうか?
もっとも私にだって、正しい意味を知る前があったわけだ。どう思っていたかは思い出せない。たぶん、なにも思っていない。
ツイッターでの用例を見ると、「ネタをつぶやいた人が、ウケに自信がないので自虐を入れておく」という使い方のようだ。
用法を誤解しているというより、「私より面白い人がいますからこの程度で許してね」。つまりむしろ、本来の用法に近いかも。
記事にも書かれているとおり、「おあとがよろしいようで」というフレーズ、実際に聴くことはまずない。
つなぎでもって、「あとの演者が到着した」なら聴ける可能性があると書かれているが、そのケースでも言う人はいないと思う。
演者のほうもそんなフレーズ、聴いたことがないはず。聴いてなければ使い方もわからない。
あらかじめ準備していないと言えないフレーズだ。実際にこう言ったら、客は驚くんじゃないか。
私も一度も聴いたことがないし、これからもないと思う。
ただし、フレーズ以前に「あとの演者が来ていない」というシーンには数回出くわしたことがある。
- 早朝寄席で、トリのはずだった柳家花ん謝さん(現・勧之助)が先に上がり、「(春風亭)朝之助さんがまだ来てません」
- 神田連雀亭ワンコイン寄席で、トリのはずだった春風亭昇市さんが先に上がり、「(桂)翔丸さんが間に合ったんですが汗が引かないので私が出ます」
- 池袋で、ヒザ前の林家彦いち師が(ラジオ生放送で)まだ来ていない、とその前の出番の三遊亭天どん師が語っていた
寝坊した、またはスケジュールを失念した二ツ目か、忙しい真打かである。
彦いち師の高座については、あいにくさして混乱はなかった。
「羽織を引く」シーンが見られるかと期待したのだが、特に何もなく。
楽屋から、高座の天どん師に声でも掛かったのだろう。
コロナでお休みになる直前の鈴本で、トリの喬太郎師が間に合わず、ヒザ前の菊之丞師が再度上がったらしい。
詳しいことはわからないが。
彦いち師のケースで、天どん師がつなぎに掛かっていた場合なら、「おあとがよろしいようで」は一応可能性がある。
だが恐らく、「彦いち師匠の準備ができたようですので、あたしはこの辺で」みたいに、ごくわかりやすく話すと思う。
すでに死語になっているフレーズに、出番はないだろう。
柳家喬太郎師の新作落語「落語の大学」には、サークル活動として「死語研究会」が登場する。
このサークルは、「毎度バカバカしいお笑いを」「おあとが大勢」などの、実際に使われることの少ない、死語を研究しているのだそうだ。
「おあとがよろしいようで」も、この仲間だろう。
もっとも「おあと大勢でございます」は、たまに聴く気がするが。
実際の寄席では、どんなフレーズが出ていただろうか? あまり考えたことがないのだが、思い出してみる。
ちなみに、噺が終わってから語るフレーズはほとんどない。だいたい、冒頭の挨拶である。「マクラ」までいかない。
本当によく聴くのは、「お目当てをお楽しみに」。
トリの師匠を楽しみに、私の一席にもお付き合いくださいという、謙虚なフレーズ。
「お気を確かに持って」というのも聴く。寄席は長いから、しっかりしましょうというもの。
トリの師匠のほうはというと、お待たせしましたなんてことは絶対ない。自分は最後に出るだけに過ぎないというポーズが粋なのである。
「私が当席のお掃除役でございます」
「私が下りますと、皆様は晴れて解放されます」
「人間、これぐらい辛抱できないようじゃいけません」
満員のときには、「楽屋一同気も狂わんばかりでございます」。
この後、「こんな日に来てくださるお客さんにはなにかお礼を出そうと提案したのですが、楽屋で却下されまして」。
これは、逆に客が少ないときにも使える。こんな日に来てくれるお客さまはありがたいと。
それにしてもこういったフレーズ、落語を知らない人は、本当にまったく知らないはず。
本当によく出るフレーズは誰も知らず、死んだフレーズだけが有名なのであった。面白いことである。